お守りは、一年以上経過すると効力が弱まるといわれていますが、知らずに古いお守りを大切に持ち続けている方は意外と多いですよね。お守りに有効期限は書かれていないので、新しいものに交換するタイミングを見つけるのは難しいものです。
そこで今回は、お守りは一年以上経ったら交換するべきか、そして正しい扱い方などについても詳しくご解説していきましょう。
お守りを持ち歩く際のポイント
 まずはお守りの効力を最大限に発揮してもらうためにも、持ち歩く際に意識したい基本的なポイントを詳しくご紹介していきましょう。
まずはお守りの効力を最大限に発揮してもらうためにも、持ち歩く際に意識したい基本的なポイントを詳しくご紹介していきましょう。
常に身につけておく
お守りは、神様が宿る依代(よりしろ)といわれており、敬意を払って大切に扱うことが必要です。近年様々なタイプのお守りがありますので、カバンにぶら下げたり家に置いたり、扱い方も様々です。
基本的な考え方としては、効果を一番実感するには常に身につけることが理想的で、体の一部になるようにすること。お守りは厄除けの意味もあるため、日頃から身につけて持ち歩くことが厄を軽減することにつながります。
お守りには、安産や恋愛成就など、色々なタイプがありますよね。その中でも健康のお守りはとくに体に関するものなので、無病息災・健康祈願などのお守りは、肌身離さず持ち歩きましょう。それが難しい場合は、普段使うバッグなどにつけておくのもよいでしょう。
心臓に近いところ
人間の体の中で、心臓はとても大切な部分。仏様や神様のご加護をいただくお守りなので、最大限にご利益を得るには心臓に近い場所に持つことがよいとされています。
命を司る心臓は、お守りの効力が持ち主の心身に直接届きやすい部分です。また、心臓は「気」が発生する源と考えられていますので、お守りの効力を効果的に受け取るにもよい場所となっています。
とくに厄除けや健康祈願などのお守りは、心臓に近い場所に持つとよいといわれています。基本的には、肌身離さず身につける心がけが大切。紐で首から下げて持ち歩くと便利かもしれません。
なお、心臓に近い場所を意識することは大切ですが、あまりこだわりすぎず、お守りで持ち主と神様がよりつながることを感じ、毎日安心して暮らす気持ちが最も重要です。
身近なところに入れる
お守りは、一年以上経過したら交換すべきといわれるように、効果を実感するためにも気をつけて扱いたい大切なものです。ひとつはお守りを持っているという方は多いはずですが、ご利益をいただくうえで、身近なところに置くことはとても重要なポイントです。
お守りとは単なるアイテムではなく、神様の分身です。ご加護を得るためにも常にそばに置き、神様の存在を意識しながら過ごすことが大切です。
また、お守りが身近にあると神様とのつながりがより意識できますし、お守りに込めた願い事が毎日思い出されますよね。何かを成就したい時、自分の努力も必要です。お守りが身近にあると、神様に見守られている安心感が湧きますし、心の支えにもなりますよね。
清潔に維持する
お守りの扱い方で大切なのは清潔に維持することで、意外と忘れてしまう人は多いでしょう。カバンの中にずっとしまってある汚れてしまったお守りや、棚の上に置きっぱなしでホコリがついたお守りなど。
「清潔にする」という気持ちは、単なる見た目の問題ではなく、神様に敬意を示すために欠かせないことです。神様の依代であるお守りは、穢れ(けがれ)を嫌がるといわれており、厄を避けるために清浄を好んでいます。
そのためお守りを汚す行為や乱雑な扱いは、効力が弱まる原因に。お守りが汚れたら水洗いはできないので、メガネ拭きのような乾いた布などで優しく汚れを拭き取るとよいでしょう。また、カバンやお財布に入れている場合は、中をこまめに掃除しておくことが大切です。
種類別のポイント
お守りは、種類ごとの特徴を活かすためにも、扱い方のポイントを意識しておくとよいでしょう。まず恋愛成就や良縁祈願、夫婦円満のお守りは、普段使うバッグやキーホルダーなどにつけることが大切。
学業のお守りは、筆箱につける、もしくはランドセルやカバンなどにつけて持ち歩くことがおすすめです。自宅で保管する際は、勉強部屋に飾っておきましょう。
金運や出世に関するお守りは、お財布に入れておくことがよいとされています。常にお金が巡るための効果的な場所になるでしょう。もし財布に入らない場合は、通帳を保管するところに一緒に入れておくこと。
貯金箱や金庫などの近くがよいといわれています。交通安全のお守りは車のミラーにぶら下げる、バイクや自転車なら鍵につける、子供の場合はランドセルにつけること。
安産祈願は家庭に関することなので、リビングのような皆の目につきやすいところに保管するとよいでしょう。
後ろポケットはNG
お守りは肌身離さず持ち歩くことが大切ですが、後ろポケットに入れるのは粗末に扱っているとみなされ、効力が弱まる可能性があります。後ろポケットは、座る時に下敷きになりますし、出し入れが頻繁にある場所なのでお守りを粗末にしていることになります。
また、お尻の近くは穢れを意味する場所なので、神様の分身をそのようなところに置くのは失礼だと考えられています。お守りは、ただ持つだけでなくどこに持つかが大切。
神様の存在を意識しながら大切に思う心が必要なのです。丁寧に扱える場所がよいので、後ろポケットではなく胸ポケットにしたり、財布やバッグに入れたり、他の方法を考えてみましょう。
正しい置き方について
 お守りの効力は一年が目安とされていますが、その期間効力を最大限に感じるためにも、置き方で意識すべきポイントをご紹介していきましょう。
お守りの効力は一年が目安とされていますが、その期間効力を最大限に感じるためにも、置き方で意識すべきポイントをご紹介していきましょう。
目線より上
お守りは、一年以上経過したら新しいものに交換したほうがよいとされていますが、効力を発揮している間、より神様に敬意を払うためにも保管場所には注意が必要です。
基本的にお守りは目線よりも上に置くべきという考え方がありますので、お札と同じく棚などの高いところに置きましょう。目線よりも上というのは、お守りには神様が宿っているためで、人間が神様を見下ろす行為にならないよう配慮が必要です。
見上げる位置は、自然と神様を敬う気持ちにつながりますので、できれば神棚と同様に自宅に保管場所があるとよいでしょう。たとえば家内安全や厄除けなどのお守りで神棚がない場合、タンスや棚の上、もしくは本棚の上段など。高いところに置くとホコリも気になるので、常に掃除を心がけてくださいね。
清潔な場所に置く
お守りは、清潔な場所に置くことが基本です。これは、マナー以上に神様を敬いご利益を最大限に引き出すための考え方で、清らかな場所を好む仏様や神様のために雑然とした場所は避けてください。
自宅で保管する場合は、常に整理整頓ができてこまめに清掃できる場所がおすすめ。もしポケットやバッグなどに入れる場合は、ごちゃごちゃしないよう整頓を意識しましょう。
自宅なら神棚が理想的ですが、こまめに整頓できるなら引き出しの中も可能です。もし箱や引き出しに入れる場合は、半紙や白い紙を敷いておくとより丁寧になります。
表面は南か東
お守りは、一年以上経ったら効力が薄れるといわれていますが、保管する際の向きによって多少影響があるので注意しましょう。神社の名前などが書かれている表面を把握して、東向きに置くことが大切です。
お札と同じく、神様が座る方角を考えることがコツになります。東方向は物事の始まり、成長を象徴していますので、神様が宿るお守りも同じく東向きがよいといわれています。
東向きが難しい場合、南向きも適切な方角なので、太陽光が当たる方角を意識してみるとよいでしょう。南向きは縁起がよいといわれており、お守りの表面が南向きになると、神様が家族やその部屋を見守ってくれます。また、「辰巳」と呼ばれる南東の方角も、よい縁や運気を運んでくる方角なので、縁結びや商売繁盛を願う場合におすすめです。
お守りの目安は一年といわれる理由
 お守りはいつまでも持っているものではなく、一年を目安に毎年交換することがよいとされています。その理由や注意点について、ポイントごとに詳しくご解説していきましょう。
お守りはいつまでも持っているものではなく、一年を目安に毎年交換することがよいとされています。その理由や注意点について、ポイントごとに詳しくご解説していきましょう。
穢れを払うため
お守りは、持ち主の身代わりになり厄やネガティブな気を引き受けてくれますので、一年以上経過するとそのお守りには厄が蓄積していると考えられています。
そのままの状態では効力が発揮できませんし、清らかな状態で持ち主を守ってもらうためにも、一年を目安に新しいお守りに替えることが大切です。お守りに限らず、お正月の縁起物でおなじみの破魔矢も同様に目安は一年とされていますので、毎年新しいものに交換しておきましょう。
常若(とこわか)の考え方
お守りは一年以上経過したら新しいものに替えるべきといわれるのは、「常若(とこわか)」の考え方も理由のひとつです。常若とは「いつも若々しいこと」「いつまでも若いさま」という意味があり、皆が元気で活力に満ちて過ごせるよう願いを込めた言葉です。
伊勢神宮が社殿を20年ごとに建て替えることもこの思想に基づいているためで、お守りも一年で新しいものに替え、清らかな神様の力をいただくという考え方があります。
一年の節目になる
一年が経過してお守りを交換するのは、初詣のような新年のタイミングが多いですよね。一年を目安にするのは、前年の感謝の気持ちを込めて古いお守りを神社に返納するという考え方があるから。
そして新しいお守りを手にして新たな年を過ごすという習慣が、期限の目安になっているのです。初詣でお守りを授かるのは、新年の願いの成就、幸運や健康を祈願するなど、目的は色々。
決してお守りを「買う」意識ではなく、神様の力を分けていただく授与品であることを意識したいですね。
願いが叶ったら手放す
必ずしもお守りは「一年」を期限として扱う必要はなく、お守りの種類によっては一年経過する前や数年後に役目を終わらせることもあります。たとえば就職や合格祈願のお守りは、願いが叶った時にお守りの期限も終わりを迎えると考えられます。
安産祈願なら出産後など、願いが成就したら感謝の気持ちを込めてお守りを返納しましょう。もしこのような明確な目的がないお守りの場合、たとえば健康祈願や交通安全、家内安全などは、一年を目安にして替えるとよいですね。
手放したくない時は?
お守りには持ち主の様々な思いが込められていますので、目安の一年が経過しても手放したくないこともあるでしょう。大切な人からいただいたものや、家宝のように大切にしているお守りなどもありますよね。
そんなお守りを手放すと逆に心身が不安定になる場合は、無理に替えることはありません。お守りは時間が経過すると穢れが蓄積されてしまうものの、持ち主の心の安定を優先するなら、無理に処分はせず大切に持ち続けることもできます。
お守りの返納方法
 一年経過したお守りや役目が終わったお守りは、適切な方法で返納しましょう。いくつかの方法がありますので、それぞれの手順について詳しくご解説していきましょう。
一年経過したお守りや役目が終わったお守りは、適切な方法で返納しましょう。いくつかの方法がありますので、それぞれの手順について詳しくご解説していきましょう。
授かったところに行く
理想的なのは、お守りを授かった場所に行って返納する方法です。神社やお寺など、お守りをもらい受けた場所に自ら出向き返納して供養してもらうこと。
多くの神社には、お守りやお札を返納する「納札所」が設けられていますので、そこに持って行ってください。もしないとしたら、受付に持ち込む場合もあるので確認後に手渡しましょう。
古いお守りを返納したら、必ず感謝の気持ちとしてお賽銭箱にお気持ちを入れて感謝しておくこと。返納のタイミングで、同じ神社で新しいお守りを購入することもできますね。
違うところに返納
旅行先でもらい受けたお守りなど、同じ場所に返納できないこともありますので、そのような場合は違う場所に返納しましょう。その際に注意したいのは、同じ宗派の寺院かどうか。
宗派が異なると神様も違ってしまい、失礼にあたるので気をつけるようにしましょう。場合によっては、他所のお守りも受け入れてくれるお寺や神社もありますので、返納先が見つからない時は事前に確認してからお願いしてください。
郵送でできるか確認
遠方の場合は郵送で返納できることもあるので、神社のウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせておきましょう。返納するお守りは、白い半紙などで丁寧に包んで、感謝の気持ちを込めたメモや手紙と一緒に封筒に入れます。場合によっては返納料がかかることもあるので、その場合は現金書留で同封するとよいでしょう。
自宅でお焚き上げ
どうしても神社に返納するのが難しい場合は、自宅でお焚き上げすることもできます。白い半紙にひとつまみの塩とお守りを一緒に包んで焼却し、その灰を可燃ごみに出すのが一般的な手順です。
お焚き上げする場合は、感謝の気持ちを込めて、庭などの燃えやすいものがない場所を選んで行います。マンションのベランダなどは危険なので注意してください。灰の捨て方は自治体によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
お焚き上げに持っていく
一年以上経過したお守りは、神社で行う「お焚き上げ」に持っていくことができます。お焚き上げとは、神仏に関するもの、故人の愛用品や遺品といった大切なものを感謝の気持ちを込めて火で供養すること。
物に宿る魂や思いに感謝して手放す意味や、清めて次の場所へ送り出すという意味もあります。お焚き上げは、寺院や神社などで読経や祈祷をして供養してもらう方法、もしくは専門の業者にお願いすることもできます。小正月に行われる「どんど焼き」も、お焚き上げの種類のひとつです。
返納したくない時の考え方
 お守りに助けてもらった、持ち主にとって意味のあるお守りなど、どうしても返納したくない場合もあります。この場合にずっと持ち続けるとどうなるのか、運気が下がってしまうのかなど、疑問もいくつかありますよね。そこで、お守りを返納したくない時の対処法や考え方を詳しくご紹介していきましょう。
お守りに助けてもらった、持ち主にとって意味のあるお守りなど、どうしても返納したくない場合もあります。この場合にずっと持ち続けるとどうなるのか、運気が下がってしまうのかなど、疑問もいくつかありますよね。そこで、お守りを返納したくない時の対処法や考え方を詳しくご紹介していきましょう。
大切に扱う
古いお守りは雑に扱うのが一番いけないことなので、とくに手放せないものは大切に扱いましょう。お守りは、古くてもなるべく身につけておくことが基本。
決して運気が下がることはありませんが、神様に対しての気持ちが薄れてしまうことは避けてください。人からいただいたものや記念のお守りなど、そのシーンを思い出しながらお守りを大切に扱うことが必要です。
お参りに行く
「お守りに守ってもらっている」という気持ちをずっと持ち続けることが重要なので、どうしても返納できない場合は大切に扱い、感謝の気持ちを込めてお守りを受け取った神社に定期的にお参りに行きましょう。
一年を目安に返納するのは感謝の気持ちを示すためでもあり、ずっと持ち続ける場合もお賽銭で感謝の気持ちを示すこと。それが古いお守りを持ち続けるコツとして最も重要です。
お守りは一年を目安に交換して正しく扱おう
お守りは、一年を目安に正しい方法で返納することが大切ですが、場合によっては返納せず持ち続けたり、自分でお焚き上げしたり、方法は様々です。
お守りは、気持ちの面でも人々をネガティブなことから守ってくれる大切なものなので、日々感謝の気持ちを込めて持ち歩くことが必要です。
☆こちらの記事もチェック!


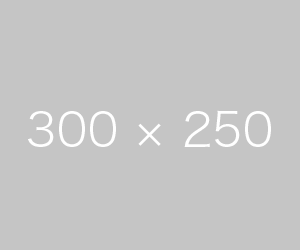
コメント