失敗しても全く引きずることがない人というのは珍しいかもしれませんが、多少気分が落ち込む程度で立ち直れる人はいますよね。仕事をはじめ、人間関係や勉強など、あらゆる場面で誰しも失敗することはあるもの。
自己成長の速度をアップさせるには、失敗からいかように立ち直るかが重要なポイントになります。失敗は誰にでもあること。だからこそ、自分に合った思考転換の方法や気持ちとの向き合い方が大切です。そこで今回は、失敗をいつまでも引きずる自分を変える方法について詳しくご紹介していきましょう。
いつまでも失敗を引きずる理由について
 失敗しないはずなのに失敗した時、または頑張ったのに失敗した時など、なかなか立ち直れなかった経験は誰しもあるのではないでしょうか。
失敗しないはずなのに失敗した時、または頑張ったのに失敗した時など、なかなか立ち直れなかった経験は誰しもあるのではないでしょうか。
いつまでも過去の失敗を引きずってしまうのは、次の成功を妨げる原因に。では、まず失敗するとどうして引きずってしまうのか、詳しい理由をご紹介していきましょう。
完璧主義のため
失敗をいつまでも引きずるのは完璧主義な自分がいるためで、失敗を恐れ、負のスパイラルに陥りやすくなります。失敗は決して嬉しいことではなく、誰でも落ち込むものですが、完璧主義な人はよりショックが大きく、立ち直るまでに時間がかかってしまいます。
失敗の原因が明らかに自分にある場合、自分は能力がない人間なのだと思い込み、次第に自己肯定感が低下していきます。いつもなら完璧を目指していてモチベーションも高いはずなのですが、成功するだろうと思っていたことが失敗すると、次の挑戦がなかなかできなくなってしまいます。
完璧主義の人は、結果を重視する傾向がありますので、よい結果が伴わないと失敗しないよう恐る恐る物事に取り組むようになります。能力がある人間に思われたい反面、失敗を恐れるために無難なことを続け、目的達成も難しくなるでしょう。完璧主義の人は小さなミスも許しませんので、自分に厳しく理想も高い傾向があります。
ぐるぐる思考のため
失敗をいつまでも引きずるのは、ぐるぐる思考のため。心理学では「反芻思考(はんすうしこう)」と呼ばれる思考パターンで、ネガティブな出来事を繰り返し考えてしまうというものです。
これは誰にでも経験があるはずで、失敗した瞬間や場面がいつまでも記憶に残り、思い出してはその時の感情も呼び戻してしまうのです。ぐるぐる思考は人間関係でもよくあり「あの時、あんなことを言わなければよかった」「きちんと仕事を終わらせるべきだった」「あの子に嫌われたかも」など、否定的な考え方がベースにあります。
ぐるぐると同じところを回るように、問題解決にならない考えを繰り返すこと。すると余計に気分が落ち込み、エスカレートすると精神的な不調をもたらす場合もあるのです。
過去の失敗を思い出すのは、決して反省や改善ではなく、未来の不安を募らせているだけかもしれません。楽しいこと以上に、なぜか人間は嫌なことばかり記憶に残ってしまいますよね。
他人の評価を気にしてしまう
失敗をいつまでも引きずるのは、他人の評価を気にしてしまうからです。ある種のクセになっている人も多く、人にどう思われるか、できるだけ高く評価されたいなどの欲求が強いことも。
これにより、周囲の視線や考え方が気になり、失敗するといつまでも気持ちを引きずってしまいます。他人の評価を気にするのは、自分を肯定的に評価できないことが関係しており、自分の判断基準の軸がしっかりしていないことも周囲に対して敏感になる理由です。
失敗経験は苦い思い出。他人に悪い評価をされたとしても、その経験から何を学ぶかがとても重要です。失敗を過度に恐れることは、他人の評価を重視しすぎるからなのでしょう。
また、中には完璧主義の人もいて、少し無理のある基準を設定してしまい到達できないことも。他人の評価を気にしてばかりいると、いつも人の視線を気にしながら暮らすようになり、プライベートでも仕事でも疲れが蓄積されてしまいます。
脳の防衛反応
失敗をいつまでも引きずるのは、脳が防衛反応を起こしているためでもあります。失敗した後、同じことを繰り返さないよう脳が同じ記憶を何度も再生していることも。
失敗してもケロッとせず、その事柄の重大性を意識して、二度と失敗しないよう脳が自分を守っていることになります。しかしこれは自己否定と似通った意味もあり、脳の防衛反応がエスカレートすると心身にも負担がかかってしまうので注意しましょう。
失敗を引きずるととても印象強く頭の中に残り、同じ過ちを避けられます。何度も思い出すのは、それだけ失敗が自分にとって苦いもので、絶対に繰り返したくない思いがあるから。
ある程度の防衛反応なら失敗の改善になりますが、ネガティブ思考は定着しやすいため、失敗から立ち直れず自分を責めている状態になってしまうのです。
脳の防衛反応は思考様式にも共通していますので、失敗が忘れられない人は、根本から物事の考え方を変える必要もあるでしょう。
自信がない
失敗をいつまでも引きずるのは自信がないことが原因で、このタイプの人は他人のミスにも厳しく、いつまでも注意したり怒ったりする傾向があります。
自信を持つことは成功の秘訣ですが、失敗は自信がある人にとっても同じく乗り越えなければいけないハードルになります。しかし自信がない人が失敗すると、自分の限界を感じてしまい、いつまでも過去を引きずることに。
更に挫折経験を重く考えすぎて、小さなミスでも人生を変えるほど大きなものだと拡大解釈してしまいます。自信がない人は、失敗することを想定しているので、極端に失敗を恐れてしまうのです。
そのため行動力に欠けてしまい、成功体験も必然的に少なくなるでしょう。他人と自分を比較して、どんどん自分が能力のない人間に思えてしまうので、何かを始める際にも不安が強く実行できなくなります。被害妄想に陥りがちなので、自信を取り戻すことからまずは始めてみましょう。
失敗を引きずるデメリットとは?
 失敗を引きずるのはできれば避けたいことですが、誰でも経験があるように、嫌な思い出ほど繰り返し考えてしまいますよね。失敗すると他人に迷惑がかかったり、自分の評価が下がったり、あらゆる影響があります。それでもなるべく早く失敗から立ち直るべきなのは、次のようなデメリットがあるからです。
失敗を引きずるのはできれば避けたいことですが、誰でも経験があるように、嫌な思い出ほど繰り返し考えてしまいますよね。失敗すると他人に迷惑がかかったり、自分の評価が下がったり、あらゆる影響があります。それでもなるべく早く失敗から立ち直るべきなのは、次のようなデメリットがあるからです。
集中力の低下
失敗を引きずると、いつもそのことで頭がいっぱいになり、集中力の低下につながります。とくに注意したいのは、仕事のミス。いつまでも引きずると更にミスが増え、悪影響を及ぼすでしょう。
忘れようと思うほど考えてしまう失敗経験。普段から思考の切り替えを意識しない人は、ずっと失敗のことを考えてしまいますので、効率的に時間を使えないかもしれません。
集中力の低下によりミスが重なるのは、原因を改善していないためで、考えないようにするだけでなく具体的な対応や改善策も必要になります。
集中力が低下するのは、睡眠不足や疲労などの身体的な要因もありますが、失敗を引きずることでストレスになり、知らない間に心身に負担がかかっていることはよくあります。
精神的に不安定になる
失敗を引きずると未来への不安が高まりますので、メリット以上にデメリットが多くなります。誰でも同じ失敗は繰り返したくないものですが、そんな点ばかり意識すると過度に慎重になり、心配することも増えます。
その不安は精神的なものとなり、失敗経験がトラウマになることもあるのです。失敗した状況に似たものがあると、自動的に不安になったり恐怖心を煽られたりすることも。
起こってもいないことを不安に感じるのは、失敗をいつまでも引きずっていることが原因です。物事を深く考えるのはよい面もありますが、失敗のようなネガティブなことを考え続けてもきりがありません。
精神的なトラブルに進展する可能性もあるので、日常生活に影響が出てくるようであれば、専門家に相談することも必要です。
相談できなくなる
失敗をいつまでも引きずると、些細なことでも大きな問題に見えてしまい、人に頼ることができなくなります。人に相談できないのは、相手に迷惑をかけたくないことや、自分の弱みを見せたくない思いが関係しています。
そして、それほど失敗を気にしている自分を周囲が理解してくれないのではないかと不安になる心理もあるでしょう。失敗は、自分で対処して改善するものと思っている人も多いはず。
相談しても既に起こったことは変えられないし、どうせ他人事で済ませられるだろうと諦めてしまう気持ちもあるでしょう。しかし仕事の場合なら、失敗を誰かに報告して改善策をアドバイスしてもらうのは得策です。
とはいえ、適切な相手がいないなどの状況もあり、世の中には失敗経験のために他人に相談できなくなる人も少なくありません。
ネガティブ思考に陥る
失敗から立ち直れずいつまでも悩んでしまうのは、ネガティブ思考のサインです。「どうせダメだろう」「また失敗するだろう」「あの時、なんであんなことを…」という悲観的な考え方は自己否定につながるので危険です。
これらは脳の防衛本能でもありますが、それが長期的に続くとストレスや不安など、心身の不調の原因にもなるでしょう。また、ネガティブ思考は他者との関わりにも影響を及ぼし、信頼関係が築きにくくなったり、自分から前向きにアプローチできなくなったりする原因でもあります。
些細な失敗をくよくよ考えてしまい、最終的にネガティブ思考に。失敗経験を完全に否定的に捉えているため、実際には存在しない他人の意見や振る舞いなどを想像し、マイナスなことにばかり敏感に反応する傾向があります。
失敗の原因を考えるコツについて
 失敗をいつまでも引きずらないためにも、原因を解明して対策を講じることが必要です。しかしその際に、ネガティブな感情や自己否定などの気持ちが関わり、原因解明ができなくなることもよくあるのです。そうならないためにも、失敗した時は次のポイントを意識して原因を見つけていきましょう。
失敗をいつまでも引きずらないためにも、原因を解明して対策を講じることが必要です。しかしその際に、ネガティブな感情や自己否定などの気持ちが関わり、原因解明ができなくなることもよくあるのです。そうならないためにも、失敗した時は次のポイントを意識して原因を見つけていきましょう。
知識や経験
大丈夫なはずでも失敗することはよくあります。その原因として考えたいのは、自分の知識や経験が十分であったかどうか。たとえば仕事のプロジェクトを任された場合、未知の分野ならしっかり勉強して知識を身につけることが必要ですし、やったことがないことに挑戦する場合は、経験不足であることを念頭に置いておく必要もあります。
新たなチャレンジには、勉強して得られる知識と経験が必要不可欠。なぜ失敗したのか考える際に、自分の許容範囲内でできるものだったかどうか判断してみましょう。
もし知識や経験不足なら、自分の努力次第で今後の失敗を避けることができますし、知らないことは引き受けず、はっきり「できない」と伝える勇気を持つことも大切です。
不注意
失敗の原因でよくあるのは「不注意」。毎日やっていることだから大丈夫と油断すると、ちょっとしたところでミスが起こり、最終的に自己否定する結果になるかもしれません。
人は常に万全の状態でいるわけではなく、疲れている時に注意力散漫になったり、体調不良でうまくできなかったりすることはあります。しかし注意すれば防げる失敗は色々とありますので、自分がどのような場面で注意力散漫になるのか、原因を特定してみるとよいでしょう。
慌てやすい人、プレッシャーに弱い人など、自分の苦手や弱点を知っておくことも、今後の失敗を回避するコツになります。
準備不足
料理のレシピをきちんと調べずに失敗するように、原因は自分の調査や準備不足という場合もよくあります。「絶対大丈夫」と確信できるまで準備をするのは難しいかもしれませんが、できる限りのことをやっておいたうえで何かにチャレンジすることが必要です。
試験の際、十分に勉強してこそ合格を勝ち取れるように、仕事も人間関係も事前の準備が欠かせません。失敗を避けるためにも、綿密な計画や情報収集、そして物事の優先順位を考えておくこと。
準備不足はケアレスミスの大きな原因ですし、計画性のなさは周囲にもよい印象を与えません。慣れや気の緩みは、準備を怠る要因になってしまうでしょう。
間違った認識
事実とは異なるように物事を自分で解釈してしまうと、失敗する可能性が高くなります。たとえば仕事なら、コミュニケーションにおける誤解がプロジェクトの失敗につながりますし、指定された期日を誤解して予定と異なる結果になってしまうこともあるでしょう。
誤認や誤解は、基本的に情報不足が関係しており、場合によっては自分の錯覚で失敗を招くこともあります。「前回はこれだけやったら足りたから大丈夫」のような考えも、認知エラーや錯覚になりかねません。
また、覚えていたはずの電話番号を間違えるなど、ちょっとした瞬間に記憶違いなども起こります。失敗を避けるためにも正確に物事を捉え、十分に確認する必要があるでしょう。
気持ちを切り替える方法
 失敗をいつまでも引きずらないためには、次の方法で気持ちをポジティブに転換していきましょう。
失敗をいつまでも引きずらないためには、次の方法で気持ちをポジティブに転換していきましょう。
失敗から原因を見つける
いつまでも失敗について考えていても、その時の気分や周囲の反応などにより、実際に原因を解明するところまで行きつかない場合が多いです。上司に怒られた場面ばかりずっと引きずるように、失敗から立ち直れないのは、あるところで考え方が止まってしまうため。
繰り返さないためにも失敗を学びの機会にして、原因分析を行いましょう。感情は切り離して考えることがコツ。手順を間違えたから、慌てていたからなど、思い当たることをノートに書き出すと客観的に事実が見えてきます。
成長の機会だと思う
失敗をいつまでも引きずるよりも、その機会にあらゆることを経験したり学んだりすることをポジティブに捉えてみてください。普段やらない取り組みに直面するのと同じで、何かに挑戦している気分になってみましょう。
失敗経験は、表面だけでなく裏側も見ることが大切。成長するために失敗はつきもので、だからこそ経験値も高くなり、自分の糧になっていきます。
過去でなく将来を見る
過去の出来事を振り返ることは大切ですが、いつまでもそこで止まってしまうのは成長できない原因です。ミスした原因を見つけたら将来に活かすように、過去ではなく次に意識を集中させること。
失敗した後、しばらく気分が落ち込むのは仕方ありませんが、そのままではせっかくの能力を発揮できませんし、負のスパイラルも起こる可能性があります。視点を少し変えるだけで、前向きな気持ちになることができるでしょう。
他人に置き換えてみる
自分の失敗はとても悲観する出来事で、実際はそれほど大したことではなくてもかなり落ち込んでしまいます。とくに完璧主義の人や周囲によく気配りする人などは、小さなミスも許せず、自分を責め続けてしまうでしょう。
そんな時は、他の人が同じ失敗をしたイメージをしてみてください。他の人がやったとしたら、それほどのことには見えないかもしれませんし、他者の失敗には寛大になれることもあるのです。
日記に書く
失敗した事実はどうしても変えることはできませんので、自分の歴史として日記などに記録しておきましょう。しばらくして読み返すと、その時の気持ちも何となく思い返すかもしれませんが、時間と共に徐々に立ち直っている自分がわかるでしょう。
「失敗しても何とかなる」という余裕を持つためにも、日記やノートに今の気持ちを書いておいてください。
失敗を引きずる自分を責める必要はない!
失敗を引きずるのは誰でもあることなので、自分だけが悪いとか、自分だけがおかしいと思う必要はありません。大切なのは、ポジティブに思考転換して前進することです。自分なりの回復策が必ず見つかりますので、まずは自分の心身をケアしてあげるようにしましょう。
☆こちらの記事もおすすめです!


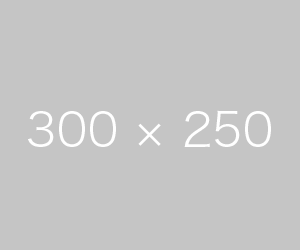
コメント